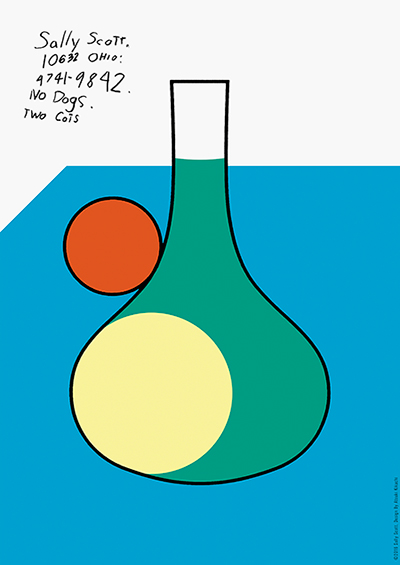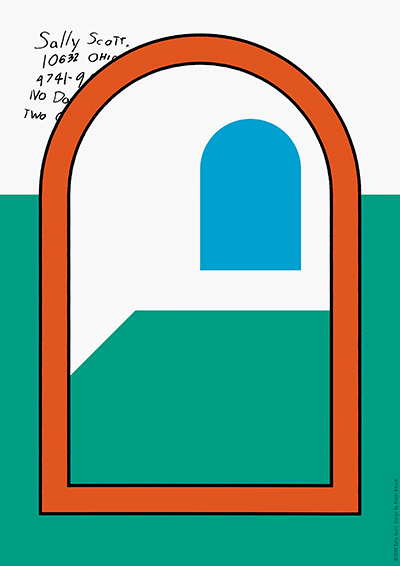独学で新しい分野を切り開いてきた、その原動力は止まらない好奇心

- Vol.144
- グラフィックデザイナー、アートディレクター 菊地敦己(Atsuki Kikuchi)氏
- profile
- 1974年東京生まれ。大学在学中よりデザインの仕事をはじめる。ブックレーベル「BOOK PEAK」を主宰し、アートブックの出版を行う。作品集に『PLAY』(誠文堂新光社)がある。
会社勤めはしない。絵を描いて⽣きていくことを考えていた。
ご出⾝は武蔵野美術⼤学ですね。彫刻科というのは少し意外です。
もともと⼦どもの頃から絵を描くことは好きでした。⾼校3年⽣の時に、美⼤に進学しようと思って美術予備校に通い始めました。予備校ではデザイン科にいたのですが、⼤学はせっかくなら⼤きなスペースでないとできないことをやろうと思い彫刻科へ⼊りました。
学⽣の頃から、いろいろなコンテストに応募し、⼊選されていますね。
『イラストレーション』誌のコンペ「ザ・チョイス」やJACA展というグラフィックアートの公募展に出品したりしていました。当時は公募展がまだ元気があったんですよ。ちらほら⼊選して、これで仕事が来るかなと思っていたら、全然で(笑)。⼤学も1年目は⼀応通っていたんですが、どうも⽔が合わなくて、2年目には休学して友⼈と3⼈でデザインの事務所をつくりました。そして3年目で退学してます……。
会社に勤めることは考えていなかったのですか。
会社勤めはまったく選択肢にありませんでした。⼤学には⼊学しましたが、卒業も考えていませんでした。特に根拠はないのですが、早く⾃⽴しないといけないと思い込んでいて。⾃分が得意なことをやって、⾃分の裁量で⽣きていきたかったんです。それが僕にとっては、結果としてデザインの仕事になっていった。
最初はどんなお仕事からはじめられたのですか。
グラフィックとウェブの両⽅ですね。従来であればデザイン事務所や会社に⼊って徒弟制度のもとで学ぶしかなかったわけですが、僕が仕事を始めた94、95年当時はちょうどデザインの分野でもコンピューターやネット環境が整い始めた時期でした。DTPやウェブは新しい環境で、空き地がいっぱいあって、なにかできそうだという開放感がありました。造形的なグラフィックデザインやイラストレーションとプログラム的なウェブデザインを両⽅⼿掛けるような事務所もまだなかったので、新しいかたちのスタジオをつくればいいと思ったんです。DTPの出現によって、デザイナーは職⼈的な専門性から解放されてアウトプットの選択肢が増えていくという⾃由な感覚がありました。
クライアントから、クリエイターとして無理な依頼をされることもあるのでは?
あまりないですよ。依頼に対して、まずクライアントと「こうしたらどうだろう?」というアイディアを出して話し合いをします。それで無理だなと思ったら断りますけど。クライアントは敵ではなくて、協働するパートナーですから。
それに、無理な依頼に応える必要はまったくありません。無理してもいい結果になりませんし、いい仕事をしなければ次の仕事にも繋がりません。
デザインだけでなく、どう届くかまで考えるのもクリエイティブ

主宰するブックレーベルBOOKPEAKより出版の『物物』
在学中にネオスタンダードグラフィックス、その後2000年に多くの名デザインを⼿がけたブルーマークを設⽴なさったんですね。
まわりに美術作家とかミュージシャンとか、何かつくっている⼈間が多くいたんです。つまりお⾦儲けとは関係なく活動する⼈たちですね。ウェブディレクターであり、バンドもやっていた⻫藤寿⼤(さいとう としひろ)くんもそのひとりで、彼がやっていたウェブ制作のチームと⼀緒になってブルーマークは始めました。デザインの仕事を軸にしつつ、非営利の活動を内包した会社をつくりたいと思って。仕事はグラフィックとウェブを合わせて総合的に受けるものが多かったですね。非営利の活動としては、アートブックとCDの出版、カフェの経営や⾳楽イベントの制作など多角的に広がっていきました。
その頃、本のデザインだけでなく、通常だと⼤⼿取次が担当する流通まで⼿掛けられるようになりましたが、それはどうしてですか。
今ではリトルプレスが⼀般的になっていますが、当時はまだ出版社から取次を通して出版する以外の⽅法が限られていたんです。⼤⼿の出版社だと売れる前提がないと出しづらいし、取次の検閲や返本制度にも疑問がありました。そういう⼤きな仕組みから外れて、独⽴した出版形態をつくりたいと思ったんです。実際に、あまり売れなそうだけどこれは⾯⽩いぞ、というコンテンツが周りにあったんですよ。それを残す⽅法を⼿探りでやっていったという感じです。
クリエイターの⽅が、そこまでされることってあまり無いと思うのですが。
普通はやらないことをするのがクリエイティブなことなので、僕がクリエイターだとするならばあたりまえのことですよね。
僕はデザインすることだけではなく、その先の受け⼿に届けるところまでのしくみを考えることもクリエイティブな仕事だと思っています。野菜に例えて考えるとわかりやすいと思うのですが、つくって持っているだけではやがて腐ってしまいます。つくったものを活かそうと思えば、流通の⽅法を考えるのは当然の流れです。流通の効率に合わせてモノをつくると内容が均質になっていってしまいますから。
インターネット環境が発達して、個⼈レベルの情報メディアが増えたことも⼤きいですね。⼀つにまとめられた⼤きなマーケットではなく、関⼼事でつながる個別のコミュニティが現実化していった時期でもあったので。実際、1,500部の画集を⽇本とヨーロッパとアメリカで⼩分けにして売った本もあります。
グラフィックデザインから企業や公共施設のブランディングまでデザインの⼒で個 性を引き出す仕事
- 青森県立美術館 VI・サイン計画
- 青森県立美術館 VI・サイン計画
菊地さんは、グラフィックデザインにとどまらず様々な分野でご活躍されていらっしゃいますが、建築家の⻘⽊淳⽒が設計された2006年開館の⻘森県⽴美術館のVI設計を担当されたのは、どんなきっかけだったのですか。
本当の話、⻘森県庁から突然電話がかかってきてVIデザインの担当に決まりましたと⾔われたんです(笑)。後で聞いたところによると、美術館準備室の学芸員の⽅が推薦してくれて内部選考をして選んでいただいたらしいです。それまで建築に関係する仕事の経験はなく、サイン計画ははじめてだったので興奮しましたね。はじめてのことは、わりと得意なんです。 やる気が出るので集中⼒が上がります。建築家が⻘⽊淳さんだったことも⼤きいですが、それ以来、建築への興味は尽きません。その後も、体育館や中学校のサイン計画など建築家と協働する機会は増えました。
VIについて教えていただけますか。
以前はCI(コーポレート・アイデンティティ)と⾔って、ロゴタイプやシンボルマーク、タイプフェイスなどを統⼀して企業の⼀貫したイメージをつくることを指しましたが、現在は企業に限らず広く使われるブランド計画の⼿法になっているので、VI(ヴィジュアル・アイデンティティ)と呼ばれるようになっています。つまり、クライアントの個性を象徴し、直感的にコミニュケーションできるビジュアル設計のことですね。
アパレルのサリー・スコットなど、⻑くアートディレクションを⼿がけられているクライアントも多いですね。
はい、サリー・スコットは⽴ち上げから15年経ちます。⻘森県⽴美術館も10年を越しました。最近だと、⻲の⼦束⼦⻄尾商店の中⻑期の計画に参加しています。ブランド計画には⻑期で関わることが多いです。ブランディングとかよく⽿にする⾔葉になりましたけど、VIを整理してそれを守っていればブランド⼒がつくわけではないですからね。継続的に変わっていくことが⼤事です。その時々の新しい開発があって、それが続いていくことでそのブランドの個性は醸成されていくものだと思うんです。⼈気があったとしてもそのままでいると、活⼒を失ってしまいます。何事も変遷こそが重要だと考えています。
ブルーマークを2010年に解散されましたが、どんな思いからだったのでしょうか?
10年活動して、まあ潮時だなと。実はパートナーだった斎藤くんとは7年目くらいの時に10年で終わりにしようかとすでに話をしていたんです。惜しまれるうちに解散した⽅がいいかなと(笑)。始めたのが20代半ばで、僕らが30代半ばになってくると新しいスタッフとは技術にも意識にも給料にも格差が出てくるし、⾼圧的になってしまう。そういう組織が嫌いなんですよ。もともと個⼈の集合体だったわけだから、会社組織を優先する必要はなかったんです。
⾃分を疑うこと、経験則に従わないことはクリエイターにとって⼤切な姿勢
- Sally Scott 2016 spring ポスター
- Sally Scott 2016 winter ポスター
菊地さんの作品を拝⾒していると、いい意味で⼀貫した作家性を感じない気がします。これも新しいことを追求しているからでしょうか。
そうですか。ただ、⾃分の美意識から離れてつくりたいとは思っていますね。ある程度まではスタイルをつくることも必要だと思いますが、様式化してしまうと何も考えなくなってしまいますから。僕は⾃分が思った通りのものなんて全然つくりたくなくて、思ってもみなかったことをやりたいんです。そうすると美意識は邪魔なんです。同じ分野の仕事をするときは、できるだけ違う⽅法をとるように努めます。プロジェクトごとに制作のルールを設定してつくることが多いのですが、それは美意識のような⾃分ではコントロールしずらい意識の殻から逃れるためでもあります。様式化できるものは、AIにでもやらせておけばいいでしょう(笑)。意外性や不可解さを含んだものに魅⼒を感じます。⾃分を疑うこと、経験則に従わないことはクリエイターにとって⼤切な姿勢だと思います。
撮影などの現場に⽴ち会われますか。
僕は現場が好きなので、ほとんど⽴ち会います。現場での即興が⼤事なので、ラフもあまり描きません。本のデザインをするときは、原稿をなるべく読みます。でも内容の説明に終わらないように気をつけます。⽂章とグラフィックが並んだときに、何か別のイメージが⽴ち上がってくるといいなと思ってデザインします。あまり知らない分野の仕事をするときは、しつこく調べたりしますが、デザインするためにというよりは、ただの好奇⼼ですね。ここ数年、⼯芸の仕事をすることが増えたのですが、これが⾯⽩くて、近現代の⼯芸史にはずいぶん詳しくなってしまいました。
これからクリエイターを目指す⽅たちにアドバイスをお願いします。
本を読むことと、体を鍛えることですかね。つまり、他者の視点でモノを⾒ること、集中⼒を持続させること。あとは、みんなに好かれようとしないことですね(笑)。多数決で新しいものは⽣まれませんから。

取材⽇:2017年8⽉24⽇ ライター:酒向充英
菊地敦⼰(グラフィックデザイナー、アートディレクター)
1974年東京⽣まれ。武蔵野美術⼤学彫刻学科中退。⼤学在学中よりデザインの仕事をはじめる。2000年にブルーマークを設⽴し、グラフィック、ウェブ、プロダクトのデザインのほか、本やCDの出版、飲⾷店経営など多⾯的な活動を⾏う。2011年解散、以降個⼈事務所。主な仕事に⻘森県⽴美術館、⼤宮前体育館のVI・サイン計画、サリー・スコットやミナペルホネンのアートディレクション、『「旬」がまるごと』や『装苑』(2013)、『⽇経回廊』などの雑誌や書籍のブックデザイン、「⻲の⼦スポンジ」のパッケージデザインのほか、美術、建築、⼯芸、ファッションに関わる仕事が多い。また、ブックレーベル「BOOK PEAK」を主宰し、アートブックの出版を⾏う。作品集に『PLAY』(誠⽂堂新光社)がある。