坂本龍一「Regret」の元ネタ。台湾原住民・サウ族の子守歌
作曲家・坂本龍一
衰えぬ名声と開催中の展覧会
去る2023年に死去した坂本龍一
作曲家にして演奏家。
かの「戦場のメリークリスマス」「ラストエンペラー」
あるいは大河ドラマ「八重の桜」の音楽担当にもろもろのコマーシャル類と、作品群はそれこそ百人千人の十指に余るほど。
名声は2023年に没した後も衰えることなく、去る2024年12月から今年の3月30日予定で、東京都現代美術館において「坂本龍一|音を視る 時を聴く」が開催されている。

坂本龍一 | 音を視る 時を聴く 2024年12月21日(土)- 2025年3月30日(日) 東京都現代美術館
坂本龍一が50年以上に渡り、多彩な表現活動を通して、時代の先端を常に切りひらいてきた。その「音の軌跡」を目で見る「形」として視覚を持って展示する試みである。
作曲家・坂本龍一
現在の我らが彼を「作曲家」として認識できているのは、彼の人生の岐路が「間違っていなかった」からである。その選択いかんでは、ラストエンペラー以下、多大なる坂本サウンズを今の我々が耳にすることは叶わなかったかもしれない。
編集者を父に、ファッションデザイナーを母として昭和27年に生まれた彼は自由な家庭的雰囲気の中で育ち、小学校時代からピアノに親しんだ。高校時代には多少の葛藤もありながらも難関の東京芸術大学作曲科に現役合格する。
そこでの出会いが、坂本の岐路になった。
音楽家・坂本龍一は生まれなかった?
彼の人生を変えかけた音楽学者
民族音楽学者・小泉文夫。
昭和2年生まれの小泉は多感な時期に敗戦を迎えるも、得意の英語で進駐軍家族と交流する中で西洋音楽、とりわけ讃美歌のハーモニーの美しさに心打たれる。
優秀な彼は医師になることを親に期待されながら、キリスト教への興味から東京大学哲学科に進み、同時に日本美術を学ぶ中で「日本伝統音楽の現代音楽につながる歯切れの良さ」を再発見し、日本人ながらそれを今まで知らなかった自身を恥じて日本民謡研究家の町田佳聲に師事する。
卒業後は平凡社の嘱託として音楽論文を執筆し、伝統音楽研究のためインドに留学、そして昭和35年から民族音楽学者として東京芸術大学で教鞭を取ることになる。
件の坂本の入学は、その10年後の昭和45年だった。
坂本龍一の音楽の基本は西洋音楽、ピアノだった。だが「西洋音楽はもうデットエンドだ。もう発展はない」と内心で思う不遜な青年でもあった。そんな思いの彼は大学も休みがちだったが、「小泉先生の授業は欠かさず出席していました」と語る。
当時の小泉文夫は、年間の3分の1は世界各国に音楽採集に出ていた。それも当時の日本人が「海外」と言われて漠然とイメージする欧米の都会ではなく、アフリカに中近東の砂漠からジャングルにまで分け入る。日本語は言うまでもなく英語すら通じない世界で現地住民の言葉を何とか覚え、伝統音楽を採集する。
スマホはおろかテープレコーダーもない時代のことだ。音楽採録作業は重い録音機器を背負っての過酷な旅程である。時には「報酬」を求める現地住人とトラブルになり、貴重な録音を放り出して逃げ出す顛末もあったという。
そんな小泉文夫に坂本龍一は憧れた。
不遜な学生ながら小泉の講義には必ず出席し、「民族音楽だけは学び倒してやろう」と誓った
「先生のお宅に行くと、すごい数の民族楽器があって、ちゃんと音も出せるようになっていて、小さな博物館のようになってました」
「先生は世界中を飛び回って、音楽でなく現地の言語もすぐに習得して、しかも都会的で洗練された人でした。とにかくかっこいいんです。3年で専攻を考える機会があったんですが、ぼくは小泉先生に憧れて、作曲はやめて音楽学者になろうかと真剣に悩んだくらいです」
坂本は自伝『音楽は自由にする』でそう力説する。
だが結局のところ
「やっぱり無理だな」
との結論に至る。
ここで諦めたのは正解であったのかもしれない。
研究者を諦め作曲家の道を進んだからこそ、後の坂本サウンドが多々生み出されたわけだから。
音楽学者は諦めた
だが坂本音楽に込められる
民族音楽エッセンス
しかしながら坂本は、民族音楽と完全に縁を切った訳ではない。
その後に生み出され続けた坂本音楽には、民族音楽のエッセンスが多少なりとも込められている。
その一例が、1994年に発表されたアルバム『スウィート・リヴェンジ』より「Regret」。
「甘い雰囲気を持ったコード進行」と「ヒップホップのドラムとベース」を組み合わせ、現代詩の様なラップを載せた曲。そのエンディングには英語でも日本語でもない、囁くような音声が入る。それこそ前記の音楽学者・小泉文夫の業績である。
1973年、件の小泉文夫は台湾でフィールド調査をした。
台湾の居住民族は、大きく2つに分けられる。14世紀以来、中国大陸本土から移住して土着した漢民族。そして漢民族以前、恐らくは石器時代から住み続けていた原住民族である。
原住民のうち西海岸に住んでいた者は移住してきた漢民族が増加する中で固有の文明を失ったものの、山岳地帯や離島、東部平原に住んでいた民族は日本統治時代を経て戦後に至っても固有の言語と文化を伝えている。小泉の台湾原住民族音楽調査は、当時の民族の分類に伴い
南部山岳地帯に住むパイワン族、ルカイ族
中部山岳地帯に住むブヌン族、ツォウ族
台湾最大の湖・日月潭の湖畔に住むサウ族
北部山岳地帯に住むサイシャット族、セディック族
東部平原に住むアミ族、ピュマ族
南東部の孤島・蘭嶼島に住むヤミ族
これら10族に及ぶ。
※これらは1973年、小泉氏の録音往時の分類です。2025年現在の台湾原住民族の分類とは異なります。
その折の録音レコードは小泉が50代で没して10年後の1992年にキングレコード「世界民族音楽大集成」として100枚組CD化、シリーズの一篇「高砂族の音楽」として発表され、2008年にはキングレコードより「台湾先住民の音楽」として単独CD化された。
※「高砂族」は、日本統治時代における台湾原住民、とりわけ山岳地帯在住で固有の文化を残していた民族の名称。
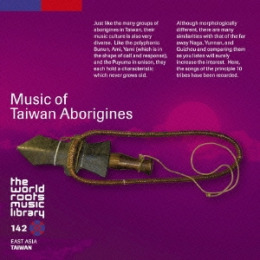
ザ・ワールド ルーツ ミュージック ライブラリー 142::台湾先住民の音楽 (画像は楽天より)
先の坂本龍一『スウィート・リヴェンジ』より「Regret」に収録された「囁き声」のような音声は、小泉文夫が1973年に現地採録した「サウ族の子守歌」である。当記事のイメージ写真に載せられた2008年発売のCDを、カバーをすり切れさせるほど筆者も愛聴している。
CD「台湾先住民の音楽」において、サウ族の音楽は「素朴」なものである。東海岸のアミ族の合唱は、現代人にとって「高度」とされている西洋の男女混声合唱に劣らない表現力を誇る。だが素朴であるからこそ、この世に生まれ出でたばかりの魂を安らげる歌であるからこそ、「子守唄」は坂本の音楽世界に自己主張することなく融合し、世界の人々の魂を安らげることになった。
さて、実のところ筆者には残念なことがある。
サウ族の音楽世界は、子守唄のみにとまらない。穀物を脱穀する際の生活道具である「杵」。その杵で臼ではなく、石板を搗く。
杵の音は同一ではない。小さな杵で石板を搗けば高い音がする。大きな杵なら低い音になる。大人数で大小の杵で石板を打ったならば、あたかも木琴や鉄琴の演奏のように旋律が奏でられる。リズミカルな「杵音」は、日常の杵つき作業から発展した、サウ族独自の芸能である。
小泉文夫は、サウ族の杵音を取りこぼしていた。それが筆者としては誠に残念である
小泉が杵音を採録していたなら、後年に坂本がその録音を聴いていたならば、どんな音楽世界が生み出されたであろうか。








