ゴールデンカムイの謎 22 日本の伝統料理だった?「ニヘイゴハン」血の腸詰
ニヘイゴハン「血の腸詰」
モンゴルから伝わった食文化?
ゴールデンカムイ2巻

第七師団、鶴見の配下として同伴の兵と共に「尾形上等兵に重傷を負わせた犯人」(杉元)を追う屈強の兵士・谷垣。彼の出身は出羽の国は秋田阿仁、マタギの里として著名な地域。彼の出身もまたマタギである。杉元を追い詰めた彼らはクマに襲われ、迷信であるところの「死んだふり」をしなくとも3人はほどなく惨死、谷垣自身はいきなり現れた最後のエゾオオカミ・レタㇻに脚を噛まれ歩行の自由を失う。
以降、3巻

自力で応急処置をするも行き倒れていた谷垣は、孤高の猟師・二瓶鉄造に救われる。そして二瓶の狩り小屋で食事を振舞われる。彼もまた、最後のエゾオオカミ・レタㇻを追うマタギ。つまり谷垣のライバルだが、雪中の行き倒れには優しい。
ここで二瓶が谷垣に振舞った料理が「心臓の丸焼き」&「血の腸詰」。
これこそ「ニヘイゴハン」
あまりにありきたりな命名法、しかしながら強烈な自負がうかがえる
「この二瓶鉄造が!この二瓶鉄造が!俺だからこそ作れたマタギ料理だ!」
との思いが。
血は栄養素の塊
石仮面かぶらなくとも食べたい
さてニヘイゴハン。
ゴールデンカムイの作画イメージにも連なる建造物が連なる愛知県の観光名所「明治村」。そこで開催されたイベントで、「ニヘイゴハン・血の腸詰」を食されたコアなファンも多かろう。
血、血液は栄養素の宝庫である。
タンパク質に鉄分、ビタミンが豊富に含まれている。
石仮面を被り人間を辞めた身ではなくとも格好の栄養源となる。イスラム教など血の食用を禁ずる宗教もあるが、宗教的タブーからは自由な立場で、生理的な忌避感さえなければ食用に活用しようと考えるのは自然な流れだろう。独特の鉄臭さ、生臭さは香辛料や香味野菜で除外すればいい。そのために世界各国に「血の食文化」が存在する。

フランスの血のソーセージ「ブーダン」
※写真は©Emmanuel.boutet
有名どころでは西洋の血のソーセージ、ブラックプディング。ユダヤ教、イスラム教では豚や鱗無し、鰭無しの水生生物、肉食獣の食用がタブー、そして血の食用もタブーなので、中近東方面に「血の食文化」は存在しない。
だが中国では血は重要な食素材だ。豚をつぶす際に血を容器に注いでおけば、自然に固まる。この「猪血」「猪紅」は刻んで唐辛子と酢を利かせた酸っぱ辛いスープ「酸辣猪紅湯」にする。
台湾では豚の血を染み込ませた糯米を蒸し、豚の血の餅「米血糕」を作る。これにピーナッツ粉を振りかけ唐芥子ダレを塗り香菜をあしらえれば屋台定番のメニュー、そしてこの米血糕は台湾式おでん「黒輪」に、コンニャクの代わりとして投入されお馴染みの具材として親しまれている。ちなみに「黒輪」は、台湾語で発音すれば「おーれん」。
そして朝鮮半島でも血は重要な食素材。固めた牛の血「ソンジ」を白菜の外側の葉と共に煮たスープ「ソンジクㇰ」は別名「解腸クㇰ」(ヘジャンクㇰ、クㇰはスープの意)とも呼ばれ、酔い醒ましには最良の料理とされる。そして西洋同様の血のソーセージもある。もち米粉に香味野菜、あるいは春雨を豚の血で練り上げて豚の腸に詰め込んだ腸詰が「スンデ」。18年も前、ヨン様が流行り始めた時分に韓国はソウル南方、水原市の民俗村で食べた。(当記事執筆のため、特別注文して写真撮影させていただきました)
ニヘイゴハンの元ネタ?
モンゴルの血のソーセージ

そしてモンゴル。二瓶がモンゴルから来た男に習った、と語る血の腸詰。モンゴル語で血の腸詰はザイダス、あるいはツォトガスン・ゲデス(血を注いだ腹)と呼ばれる。これを作るには新鮮な血液と腸が不可欠なので、まずは羊を処理しなければならない。さてモンゴルでは、家畜を屠畜するには2種類の手順がある。一つ目は、家畜の眉間、あるいは脊椎を強打し昏倒させる方法。モンゴル語で「ノガスラフ」と呼ばれ、牛など大型家畜に用いられる。二つ目はモンゴル独自とも言える「オルルフ」。これは羊にもちいられる屠畜法で、まず羊を仰向けに倒して胸を裂き、そこに素手を突っ込む。そして心臓を探り当て、人差し指と中指で心臓に連なる大動脈をプツンと切断。羊は胸腔の中に大出血し、そのまま絶命する。放血された血は胸腔の中に溜まるため、一滴も無駄になることはない。
絶命した羊は皮を剥ぎ腹を開いて解体されることになるが、長さ25mはある小腸は内容物、未消化の草や糞をたぐり出してきれいに洗い、血を詰め込こむ。これが前記の血の腸詰だ。もちろん、独自の屠畜方法で胸腔内に溜まった血を使用する。この血に小麦粉やネギなどを混ぜ込み、癖を押さえる工夫もあるという。なお小腸よりも太い大腸には、血ではなく刻んだ肉部やモツを詰め込んで茹でる。この料理はモンゴル語で大腸を意味する「ホス」の名で呼ばれる。部位の特性によって調理法を使い分けるのが面白い。
血を厭う日本本土の文化
だが沖縄では血も食用となる
一方日本では…
かつて琉球王国だった沖縄では、中華同様に豚を巧みに調理した。「豚で役立たないのは鳴き声だけ」と称されるくらい、徹底的に利用した。豚を屠畜する折は血を器に受けて固め、豚の血入りの野菜炒め「血いりちー」として食する。
だが飛鳥時代以来、時の権力者に庶民までもが篤く仏教を信仰していた日本本土では、殺生禁断による忌避感、あるいは仏教伝来以前からの「血のケガレ」の観点からか、獣肉、それも血を率先して食する食文化は存在しなかった。
山中で狩りを生業とするマタギも同様。獣肉、あるいはモツは汁物、煮ものとして美味しくいただくものの、血液は放血されるままで特別な価値は見出されていない。
そしてアイヌ民族の社会も同様。熊の血は、射止めた者のみが率先して飲む権利がある。だが熊、あるいは鹿であっても血を率先してあつめて特別な料理を作る風習は無かったようだ。もっとも計画的に得られる「飼育した家畜」ではなく、突発的に得られるとも言える「山中の野生動物」ゆえ、血を要領よく集められる機会に恵まれない。
だから「ニヘイゴハン・血の腸詰」はルーツをモンゴルに求めた。
日本にもあった血の腸詰
平家の落人の里の料理
日本本土には「血の食文化」ましてや「血の腸詰」が無い、だから「ニヘイゴハン」はルーツをモンゴル、後にきな臭くなる昭和初期の言葉を用いれば「満蒙」に求めた…だが驚くなかれ「血の腸詰」の食文化は日本本土にも「一部の伝統食品」として存在していたのだ。
ゴールデンカムイの主要参考文献のひとつ、農文協の『日本の食生活全集47 アイヌの食事』、その同シリーズに『栃木の食事』がある。
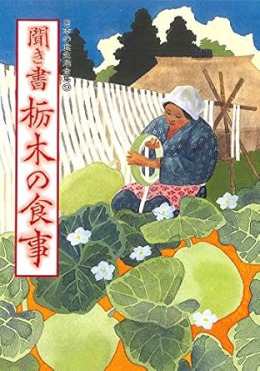
大正から昭和初期にかけての時代。明治以来の文明開化、欧米化に染まりつつも、日本伝統の衣食住が生きていた時代。そんな貴重なタイミングの、栃木県各地における庶民の日常食、ハレの特別食を詳細に追った良著。鬼怒川や渡良瀬川流域の水郷、稲作地帯に那須野が原開拓地の畑作地帯、あるいは両毛の山村。その中に鬼怒川上流の栗山村、現在の日光市栗山地区の食文化を追った一節がある。
平家の落人が隠れ住んだ、との伝承もある栗山村は純然たる山村である。耕地に恵まれず水田稲作など思いもよらない当地では、日常食は購入した米に自家耕作の稗を炊き込んだ稗飯か大麦のみの「ばくめし」、あるいは蕎麦団子。だが山の恵みは豊かである。春はゼンマイにワラビにコゴミ(クサソテツ)、あるいはトトキ(ツリガネニンジン)、秋になればトチの実に栗が実る。マイタケにシメジにムキタケと茸の類も美味い。そして冬を迎えれば狩猟シーズン、現代では禁猟となったツグミの焼き鳥、ヤマドリの身を刻んでチタタㇷ゚のツミレ団子にして汁に入れた「山鳥もち」、ばんどり(ムササビ)や兎をダイコンやネギと共に醤油と煮〆た「大根ざっぱ」、そして日本の猟師、マタギ料理の中でも恐らく鬼怒川上流の栗山、川俣方面でしか作られない珍味が「それそれ」である。
それそれ…妙に調子がいい名称の由来は不明だが、鹿やツキノワグマ、カモシカなど大型の獲物を得た時のみ作られる。大型の獲物を射止めて解体する折、内臓の「結腸」の部分を長さ30㎝ほどに切り、中の汚物をしごき出した上で裏返す。そして一方の端を麻糸で縛って袋状にした上で血を注ぎ込み、一杯になったら残る一方も糸で結び塞いで獲物と共に村へ持ち帰る。
炉に火を熾して湯を沸かし、先の「生き血の腸詰」を放り込み、「中が固くなるまで」完全に火を通す。
輪切りにして醤油をつけて食べる。
まさしく「ニヘイゴハン」血の腸詰ではないか!
ゆであがった血の腸詰「それそれ」は、中の血が煮凝り上に固まっている。「きょろきょろ」とのオノマトペで表現される舌触りが、なんとも言えないという。
狩りで獲物を得る。
新鮮な獲物を得たときにのみ作られる血のソーセージ。
栃木の一部にしか伝承されていなかった、というのが残念で残念で…
(冒頭のイメージ写真は、韓国の血の腸詰「スンデ」です)
※参考文献
『日本の食生活全集 栃木の食事』農文協 1988年
『世界の食文化 モンゴル』農文協 2005年








