“アート”を超越して新しい社会の萌芽を育てる
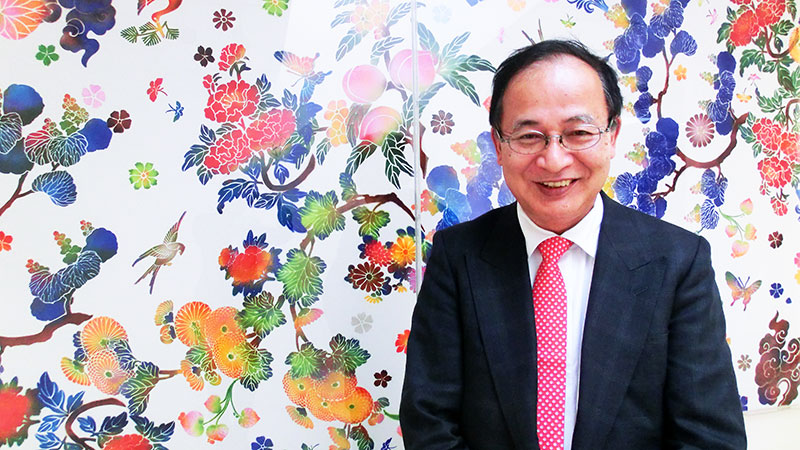
- Vol.138
- 大地の芸術祭、瀬戸内国際芸術祭 総合ディレクター 北川 フラム さん
- (写真)大巻伸嗣作品の前で
“現代アート界"の外にも 生活芸術はあるんです

イリヤ&エミリア・カバコフ「棚田」 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 撮影:中村脩
2000年から始まった「大地の芸術祭」を皮切りに、いま日本各地で“地域アート"がブームになっています。第一人者である北川さんは、この傾向をどのようにご覧になっていますか。
いま大きな傾向として、台湾や中国などアジア諸国から多くの人が瀬戸内や新潟へ視察に訪れています。僕が書いた本も台湾や中国、アメリカで翻訳されましたし、昨年の瀬戸内(国際芸術祭)には、150人くらいの海外サポーターが手伝いに来てくれました。この現象は、驚異的だと思っています。狭いアート業界から見ると、日本は市場としても大きくありませんし、欧米の現代アートの主流からみると、黄昏の国。でもなぜか地方に活気がある。それは資本主義の倫理性が失われて、いま第三期のグローバリゼーションを迎え、もう一度自分たちと自分たちの地域とのつながり、そこから世界とのつながりに立ち返ったからじゃないかと思います。アートには、歴史や文化の良さを引き出し、そこに生活する人々や訪れる人々の、未来につながる土地の記憶を呼び起こす力があります。いずれの芸術祭でも、アート作品を展示することによって、その土地の歴史や文化、そこに暮らす人々の生活の独自性が再発見されたことが大きかったのではないでしょうか。芸術祭の狙いとしても、本当に観ていただきたいのはアート作品以上に、その作品が置かれた背景であり地域性なのです。ですから、経済効果も喜ばしいことですが、例えば瀬戸内国際芸術祭の開催島である男木島で休校になっていた学校が再開したり、日本で最大の産業廃棄物不法投棄事件が起こった豊島、ハンセン病の隔離病棟があった大島が活性化し始めたとか、そういった変化が嬉しいですね。それはアートという領域を越えて、新しい社会の重要な萌芽であると思っています。
「地域全体が作品のカンバスであり、美術館である」という芸術祭の概念は、とても斬新でしたし、その発想自体がアートだとも言えるのではないかと思いました。
アート業界の一部からはご批判をいただくこともありますが、その一方で「戦後さまざまな発明品が生まれた中で、大地の芸術祭ほど優れた発明品はないんじゃないか」と言ってくれた批評家もいましたね。僕自身がもともと、公募団体や美術館を最高峰とするアート界のヒエラルキーに共感できなかったんです。絵画の描き方が評価される美大の価値観や、欧米で流行った現代アートのテーマを持ってきて日本の美術館で同じように展示することに、どれだけの意味があるのだろうと思いますね。例えばニューヨークのMOMA美術館の展示は個人的に好きですけど、そうしたヒエラルキーの外にもアートや生活芸術はあるんです。資本主義社会が行き詰って、世界各地で根本的な問題が起きてきている時代に、それをどうしたらいいのかを考えることがアート本来の役割ではないのかなと思っています。それをニューヨークのMOMAやイギリスのテートモダンを最高峰として、それをいかに日本で翻訳するかに熱心になることはアートとは思えないので、「○○さんが出展しているから素晴らしい」と評価するような狭い文脈の中で生きているアート業界にはあまり興味がありません。音楽に例えるなら、ソナチネやチェルニーを勉強して音大に入ることで真の音楽家になる……というようなことじゃないと思うんですよね、アートって。
ただ、日本のアート業界はそういう文脈のもと発展してきた経緯や歴史があるので仕方ないと思っていますから、それに対しては何も言いません。でも僕はそういうアートには興味がないんです。せっかくグローバリゼーションで他国と繋がれる時代なのだから、どうやって世界のアーティストたちの力を借りて何か生み出せるか。そういうことを少しずつやり始めています。
アートとは自然と人と文明の 関係性をあきらかにすること

「アート」の本質って、いったい何なのでしょうか。
アートとは、アーティフィシャル、つまり人間と自然の関係を人の手を使ってあきらかにしたものだと思っています。北斎は、さまざまな角度から富士山を描いて、人と富士山との関係を明らかにしました。ちょうどミケランジェロが、絵画でもアートでもやったことと同様に。今まさにその本来の意味に立ち返っているのだと思います。また、アートは唯一、人と違うことが褒められる分野。それは全体主義に傾きがちな社会や政治に逆行できる最後の手だてだと思っています。
20世紀は「都市」の時代でした。都市の課題を解決していくことが、アートのテーマでした。その頃に台頭したのが、もっとも多様にいろんなことに対応できる優れたユニヴァーサル・スペースという考え方です。ようするに、ギャラリーにもなるし居住空間にもオフィスにも使えるミニマルな空間が優れたデザインであるという価値観ですね。それは現代にもまだ残っていますが、その考え方が土地固有の文脈を捨象したのだと思います。都市には刺激と興奮、大量消費、合理性、処理能力の高さがあります。しかし果たして、それは人間にとっていいものだったのだろうか?という疑問が生まれてきました。そこから、アートは彫刻や絵画だけではなく、地元の食だったり祝祭だったりを通じて、どう地域と関わるかを考え、さまざまな表現を通じて実践していくことが時代の潮流になってきました。都市が中心の時代は終わったんです。
大地の芸術祭も瀬戸内国際芸術祭も大変盛り上がっていますが、いま抱えている課題は何ですか。
地元の人の高齢化ですね。大地の芸術祭では最初の立ち上げに関わってくれた人たちが、20歳年をとってる。当初は、都市の若者と地域のじいさま、ばあさまとでやってきたので、今、その後継者をどう育てていくかが目下の課題です。芸術祭でもっとも大切なことは、その地域の自然とのかかわりの中で伝えられ、積み上げられていった知恵とものづくりの伝統を活かすことだと思っています。例えば、「大地の芸術祭」は3年に1度の夏季開催ですが、冬季の取り組みを本格的に始めました。世界有数の豪雪地である越後妻有の魅力をアートの力で掘り起こす『SNOWART』(スノワート)というイベントを今年も3月に開催します。見どころは雪の中で花火を打ち上げる「越後妻有 雪花火」ですが、会場に2万個くらいのLEDを設置して“光の花畑"を作るんです。でも、普通の美術展とは違って、会場になるのは豪雪地帯。さらに都会の雪と違ってベタ雪ですし、ある日突然、一晩にして何メートルも雪が積もります。アーティストは会場をデザインできても、地元の人たちから雪の特性を学ばない限り、実際には現場で何も作れません。必然的にアーティストと地元のおじいちゃんおばあちゃんの交流が生まれるんです。その結果、アーティストは積雪量や雪の透過性を計算することができ、雪上にふわっと灯かりが燈るように光を工夫して幻想的な空間を作り上げます。
素敵ですね。北川さんは今後もディレクターとして草の根的に関わって行かれるのでしょうか?
ずっと活動を続けていきたいですね。瀬戸内国際芸術祭の「こえび隊」という、地域に入って作品の設置活動や解説を行うボランティアグループがあるのですが、そのスタッフが先日、20年後の未来予想図を描いてくれました。その中で年老いた僕は、受付でスタンプを押していましたね(笑)。そうなれたら嬉しいです。
取材日: 2016年12月19日 ライター: 河本洋燈
北川フラム (きたがわ ふらむ)
1946年新潟県生まれ。アートディレクター。アートフロントギャラリー主宰。74年東京藝術大学卒業。「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」、「にいがた水と土の芸術祭2009」、「水都大阪2009」、「瀬戸内国際芸術祭」の総合ディレクターなど、地域の魅力を再認識させるイベントやまちづくりに携わる。06年度芸術選奨文部科学大臣賞、16年紫綬褒章など受賞多数。近著に、『美術は地域をひらく 大地の芸術祭10の思想』(現代企画室)、『ひらく美術』(筑摩書房) 『直島から瀬戸内国際芸術祭へ』(福武總一郞氏と共著、現代企画室)。





