自分の居場所みたいなものを 自覚してないとものは作れない
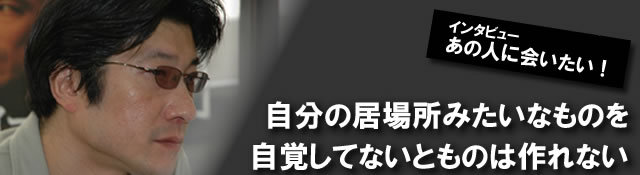
- Vol.5
- 映画監督 阪本順治(Junji Sakamoto)氏
話題の超大作『亡国のイージス』は、ハリウッドのスタッフを起用した意欲作でもある。
試写を拝見しました。面白かったです。
ありがとうございます。老若男女に楽しんでもらえる作品になったと思っています。ただ、政治的な内容が濃いので、若い人、中学生くらいには難しいかなと思わないではない。でも、僕たちが中学生の頃も、理解しきれない大人の映画を、背伸びして観てましたからね。そういう楽しみ方をしてもらえればと思います。
今回の作品は編集や音楽にハリウッドのスタッフを起用していますね。阪本さんの望んだことなのですか?
いえ、プロデューサーの構想です。ハリウッドで仕上げをするということに関しては、1回は抵抗しましたよ(笑)。後に、先入観であったことがはっきりするのですが、こういう、日本ならではの話、外人さんがわかるのかという疑問はあった。でも、抵抗しつつ、やってみたいなという自分もいたわけです(笑)。僕は、手がける仕事に関して未知数がいくつあるかというのが、監督業におけるスリルになると思っていますから。
ハリウッドのスタッフと仕事をするということに関して、特別な心構えは持っていた?
大切なのはハリウッドとやるということではなくて、ハリウッドの誰とやるかっていうことですよ。今回は、撮影中にプロデューサーがロンドンやハリウッドで面接をし、デモテープを持って帰ってくれて、そこからチョイスさせてもらいました。編集のウィリアム・アンダーソンさんにしても、音楽のトレヴァー・ジョーンズさんにしても、ハリウッド的な作品ばかりをやってきた方ではありません。ただ、それでもやはり、「ハリウッドではこうするんだよ」と押し付けられることへの危惧は、確かにありました。
で、実際は?
さきほども言いましたが、先入観でした。つくづく思ったのは、システムは違っても、作品への向き合い方に共通項は見出せるんだということですね。彼らは、ハリウッドのスタッフといってもハリウッド生まれのハリウッド育ちなんかじゃない。ウィリアムさんはアイリッシュだし、トレヴァーさんは南アフリカ人。だから、日本人が、日本人ならではの映画を作るのは当然という見識を持ってるんです。もうひとり、クリスという若手の音響スタッフがいて、彼は生粋のアメリカ人なんですが、音響のサンプルを持って来た。本当にハリウッド的なスペクタクルな音だったんだけど、「ハリウッドではこうするんですが、あなたの作品はこうではないですよね、たぶん」と言って、本当に一度聴かせただけで引っ込めちゃいました(笑)。
ウィリアム・アンダーソンさんの編集は、どうでした?
長尺に編集したものに字幕をつけて渡したんですけど、換骨奪胎というか、たくさんの発明と大胆な取り組みに驚かされました。アメリカに渡って、初めて彼の編集したものを観たとき、もう、一観客になってしまいましたね(笑)。大胆なシーンの入れ替えがあって、僕が撮影しながら作ったリズムが、いい意味で壊されてました。刺激的でした。
で、仕上がった2時間7分の本編は、納得のいくものになった?
想定していた間合いをバッサリ切られてたりもしたんだけど、ものごとには乱暴なくらいにされないと気づかないことがあるんだなあとつくづく思いました。尺としてはもっと許されていましたが、ウィリアムさんに「劇場から出た帰り道で、観客にはいろいろ考えてもらえたらいいと思い切り、一気に観せてしまうのも手だよ」とアドバイスされて納得しました。



映画の真ん中には俳優がいなければならない。 アクションは顔を撮らなければならない。
この作品で、阪本さんがもっとも力を注いだことは?
どんなに立派なセットや撮影や特撮があっても、映画は、俳優さんが真ん中にいなければ成立しないということですね。
そのために必要なのは?
言葉、ですね。僕の意思を俳優やスタッフに伝えるための言葉。特に俳優さんたちとのコミュニケーションは、僕がもっとも大切にすることです。今回は力のある俳優が数多く参加していたので、正直きつかった。撮影の終盤には、体力的に限界を超えてしまって言葉が出なくなってしまったことも。そのせいで、途中で撮影をストップしてもらったほどです。監督になって初めての経験です。
言葉は、そんなに大事なんですか?
映画っていうのは、人の人生を切り取って演じるわけじゃないですか。だから俳優は、その人物がそこまでどう生きてきたかをどう解釈するかが演技のポイントになる。ときには原作に戻って正解のこともあるし、そうでないこともある。特に今回は、設定を原作から大きく変えている部分もありますからね。あらゆるシーンに、演出家と俳優との間で新たなすり合わせの必要が生じてくる。そんなときには、言葉しかないんです。
日本を代表するスターたちとの仕事は楽しかった?
優れた俳優さんは、みなさん意思があります。日常の生活から意思を持って生きていて、それが個性になっている。演出っていうのはある意味、「Help me」です。演出家が事前に練りに練った構想も、現場での俳優のアイデアにかなわないことも多いし、力のある俳優はそこが優れているとも言える。俳優のアイデアが良ければ、カメラ位置を変えて撮り直すことだってありますよ。
アクションシーンで心がけたことは?
アクションは、人の顔を撮らないとなんの動きも生まれない。『鉄拳』のときに気づいたことです。彼はなぜ彼を殴るのか、そこに至ったいきさつを顔が語っていなければいけないんです。殺陣は優れたアクションコーディネーターと真田君に任せて、僕は、殴られる直前の、あるいは直後の「この顔が欲しい」ということに注力してました。
主役の真田広之さんが、中年の熱血自衛官を演じているのが印象的でした。
撃たれて、よろけて、こけるときにも色気があるのがスター。だからあの役は真田君でなければならなかった。今回の役は中年の自衛官だから、そんなに鋭く動けてはいけない。でも、どんくさい動きをすることにこそ、身体能力がいるんです。能力のない人は、よろけたら止まれなくて、カメラのフレームから出ちゃいますからね。
もっとも難しかったシーンは?
一番悩んだのはラストシーンですね。本でいえば読後感をどこに持っていくか。僕のこれまでの作品は主人公が無残に死んでたんだけど、今回のテーマは「生きろ」ですから(笑)。で、出した結論は主人公が登舷整列(とうげんせいれつ/観艦式や出港のときなどに両舷に艦の乗員が整列すること)をしている若い自衛官の横顔を見るという終わり方。真田君とは、どんな気持ちでそこに立つかということを入念に話し合いました。
さすがに自衛隊の協力がある映画は、シーンの迫力が違いますね。
今回は、プロデューサーが2年かけて信頼を得ています。お願いをし始めた当初は「ゴジラだったらよかったんだけどね」と言われたそうだけど(笑)、クーデターを起こす話ですからね。よく協力を得られたもんだと思います。
本物の自衛隊ならではエピソードは?
撮影の多くは訓練に便乗してのものでした。訓練の合間ですから、時間が来ると艦のスピーカーが「映画協力始めっ」って指令を下すのが感動的だったですね(笑)。
大作を飛び越えて、超大作。 プレッシャーがないといったら嘘になる。
制作費12億円の大作に起用されて、プレッシャーはありませんでしたか?
小規模、中規模やったことあるけど、大作は未経験。そんな僕に、大作を飛び越して超大作ですから。オファーをくれた小滝さん(小滝祥平氏)に、「なんで僕なんですか?」と真っ先に聞きましたよ。返答は、「『ぼくんち』を観て」でした。かなりトリッキーなコメントなんだけど(笑)、結局、「人間触ってくれ」なんだなと解釈しました。 それと、僕が現役でいたということが重要だったとも思っています。たとえば『ぼくんち』が6年ぶりに撮った久々の作品だったとしたら、そういう判断はしてもらえなかったのではと思う。『ぼくんち』 があって、翌年『この世の外へ クラブ進駐軍』を撮って、阪本はこの後どこへ行こうとしているのだろうという興味を持ってくれたからこそ、未知数の賭けをする決心をしてくれたような気がします。
『どついたるねん』の公開から数えると、満15年。16年目に入っていますが、そういう区切りみたいなことは意識しましたか?
そんなことより、思うのは、黒澤明さん『七人の侍』44歳、深作欣次さん『仁義なき戦い』43歳、大島渚さん『愛のコリーダ』42歳、やべえ!もうその歳を越えてるぞ、ってことですね(笑)。年数は15年ですけど、まだ14本しかやってないですからね。やりながら勉強していると考えていますが、それにしてはこんなにしか成長できてないのかと反省します。



自分の居場所を自覚しないと、ものは作れない。
若手クリエイターたちに、エールを送ってください。
自分の居場所みたいなものを自覚してないとものは作れないなあというのが今の感想です。映画の世界でなにがしたいの?と聞くと、大抵の若者は「映画で感動と勇気を与えたい」と答える。そんなとき僕は、「自分が何者かわかっている?」って聞きかえします。自分はなにもできないんだというところから始めなきゃいけないと思います。 また、人との関係性に自信のない人は、まずどんどん作っていくべきだと思う。今のデジタル機材があれば、簡単ですからね。そして、次の段階として誰かとコミュニケーションして集団でものを作ることを試せばいい。映画は、終局的に集団でしか作れないものだけど、できることから始めないとなにも始まりませんからね。
Profile of 阪本順治

監督デビュー作、89年『どついたるねん』で芸術選奨文部省大臣新人賞、日本映画監督協会新人賞、ブルーリボン賞最優秀作品賞他、その年の各映画賞を総なめにし、鮮烈なデビューを飾る。その後もコンスタントに作品を撮り続け、00年『顔』では日本アカデミー賞最優秀監督賞、キネマ旬報ベストテン第1位、毎日映画コンクール日本映画大賞、報知映画賞最優秀監督賞など、再び大旋風を巻き起こす。00年深作欣二監督の名作シリーズを新しいテイストで再構築した『新・仁義なき戦い。』、02年金大中事件に潜む闇に迫った『KT』、03年西原理恵子原作のベストセラーコミックを映画化した『ぼくんち』、04年太平洋戦後の米軍基地クラブのバンドマンを描いた『この世の外へ クラブ進駐軍』など最近は意欲的に様々なジャンルに絶えず挑戦している。
| 【作品】 | |||
|---|---|---|---|
| 1989 | 『どついたるねん』 | 1998 | 『愚か者 傷だらけの天使』 |
| 1990 | 『鉄拳』 | 2000 | 『顔』 『新・仁義なき戦い』 |
| 1991 | 『王手』 | 2002 | 『KT』 |
| 1994 | 『トカレフ』 | 2003 | 『ぼくんち』 |
| 1995 | 『BOXER JOE』 | 2004 | 『この世の外へ クラブ進駐軍』 |
| 1996 | 『ビリケン』 | 2005 | 『亡国のイージス』 |
| 1997 | 『傷だらけの天使』 | ||





