小説グルメ・泉鏡花『眉かくしの霊』
怪奇小説家・泉鏡花は
その実はグルメ作家
明治の怪奇小説家・泉鏡花の「高野聖」を読む
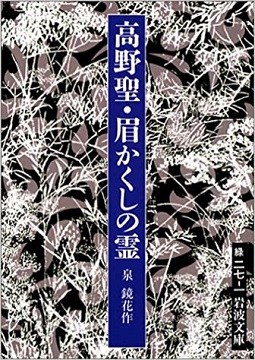
時は明治時代、汽車で旅する主人公が、老僧と知り合いになる。
その老僧が若き日に体験した奇怪な出来事。
よこしまな旅人を馬に変身させて売り払う妖女…
奇怪にして妖艶な泉鏡花の作品世界、その代名詞ともいえる本作品
作品内で、主人公と老僧を結び付けるのは「ちらし寿司」である。
主人公が名古屋の駅弁として買った件のちらし寿司は一番安い品。
蓋を開けた主人公は思わず絶叫する
「やぁ人参と干瓢ばかりだ」
それを潮に、同席で偶然にも同じ寿司を買い求めていた老僧と知り合いになり、かの怪談語りへと至る。
泉鏡花は「食」の作家でもある。
怪奇ウンヌンより前に、彼がつむぐ食卓描写はあまりにも美的感覚に優れている
信州奈良井の怪奇事件
事件の伏線は「ツグミ鍋」
私が手に取ったのは、岩波文庫版の「高野聖」
表題作の後ろに載せられた作品は「眉隠しの霊」
信州中山道の宿場町・奈良井。
その旅籠に逗留する主人公が体験する怪異譚がモチーフだが、この作品とて屋内の調度品描写、そして食卓描写の馥郁たる描写に涎が湧き出だすことしきり。
以下、抜き出し
さて膳だが、――蝶脚の上を見ると、蕎麦扱いにしたは気恥ずかしい。わらさの照焼はとにかくとして、ふっと煙の立つ厚焼の玉子に、椀が真白な半ぺんの葛くずかけ。皿さらについたのは、このあたりで佳品と聞く、鶫を、何と、頭を猪口に、股をふっくり、胸を開いて、五羽、ほとんど丸焼にして芳しくつけてあった。
「ありがたい、……実にありがたい」
前夜の宿では生煮えのうどんをあてがわれ食傷した主人公、この奈良井の宿に上がり風呂を使えば、座敷には素晴らしい食膳が用意されていた。それが上記の抜き出し。
山国ながらワラサの照り焼き、厚焼き玉子、そして「ツグミ」なる野鳥の付け焼き。その味わいがいたくお気に召した主人公は、その鶫をアツアツに煮付けたらどんなにか好かろと、あえて「鳥鍋用」に別口注文する。ツグミは笊にまだ5杯分あるという。
実は、このツグミ料理が大いなる伏線でもあったりするのだが
ともあれ主人公はツグミ鍋を堪能する。
……昨夜は、あれから――鶫を鍋でと誂えたのは、しゃも、かしわをするように、膳のわきで火鉢へ掛けて煮るだけのこと、と言ったのを、料理番が心得て、そのぶつ切りを、皿に山もり。目笊に一杯、葱のざくざくを添えて、醤油も砂糖も、むきだしに担ぎあげた。お米が烈々と炭を継ぐ。
越の方だが、境の故郷いまわりでは、季節になると、この鶫を珍重すること一通りでない。料理屋が鶫御料理、じぶ、おこのみなどという立看板を軒に掲げる。鶫うどん、鶫蕎麦そばと蕎麦屋までが貼紙を張る。ただし安価くない。何の椀、どの鉢に使っても、おん羮、おん小蓋の見識で。ぽっちり三臠、五臠よりは附けないのに、葱と一所に打ち覆まけて、鍋からもりこぼれるような湯気を、天井へ立てたは嬉しい。
行間から美味さがじわっと滲み出すような描写。出し汁に浸りつつ煮えたツグミの身を噛みしめれば、芳醇な香気が喉から鼻へフッと抜ける。
当小説が発表されたのは大正時代、関東大震災の翌年。
だが令和のわれわれがこの小説にあこがれ、ツグミ料理をあつらえるのはまず不可能だ。
今や御法度のツグミ料理
海原雄山は何故その味を知る?
ツグミ。
スズメ科ヒタキ属の渡り鳥

夏にシベリアで繁殖し、冬になれば越冬のために南下して日本に渡る。
そこを人間に捕えられ鍋料理にされる。
ツグミほか野鳥は「かすみ網」を用いて捕らえる。
谷筋の野鳥の通り道にこの網を張り巡らせば、鳥は衝突して簡単に捕らえられる。
だが、お目当ての種はもとより、通りかかる鳥すべてが文字通り一網打尽にされてしまう。
そこで鳥類の保護の名目として、戦後の昭和22年にかすみ網での猟、後にはかすみ網の所持そのものが禁止された。
ツグミは今や幻の味で
だが、ツグミは美味いという。美味いからこそ、小説のネタになる。
主人公が堪能し、後の怪奇の伏線になる。
そして「美味しんぼ」のネタにもなる。
海原雄山を激怒させた、伝説のネタ。
問題は、海原や山岡が「なぜツグミの味を知っているか」ということなのだが…
それを突っ込むのは、やはりヤボというものだろう。








