『ごんぎつね』考察 鍋の中で「ぐずぐず」煮られていたものの正体は?
「鍋の中で煮ていたのは何ですか」
「母親の遺体です」
去る7月下旬、ひとつのネットニュースが物議をかもした。
犯罪や貧困をテーマに長年取材、執筆活動を続けるルポライター・石井光太氏の新著『ルポ 誰が国語力を殺すのか』が発端だった。

その新著を世に出すに当たり、石井氏いわく
「今の子どもは『ごんぎつね』を読めない」
取材のなかで、とある小学校教師が語る。
昭和戦前期の童話作家・
新美南吉氏の代表作『ごんぎつね』の一場面。
兵十という男の母親が死に、その葬儀が行われている。
外のかまどでは何かが煮られている。
教師は物語を児童一同に読ませたうえで、一つの課題を出した。
「鍋の中で煮られているのは何ですか」
その問いにかなりの数の児童がこう答えたという。
「母親の死体を煮ている」
「母親の遺体を煮て消毒している」
冗談でもなんでもなく、まじめな回答である。
これを受けた石井氏、並びに「識者」は嘆く。
そして悲憤慷慨する。
「教育格差の増大」
「今の子どもは『葬式で振舞い膳を作る』風習をしらないから仕方がない」
「葬式を何のためにするのかわからないのか。ここでは親を亡くした兵十の悲しみを読み取らなくてはならないのに」
だが筆者はこのニュースを見聞きしても驚かなかった。
むしろ、安心した。
40年ほど前の昭和後期。
同様の「誤解」を筆者自身がしかけたからである。
美しい物語の描写
葬式の詳細はうかがえない
なぜ誤解されるのか。
それは「ごんぎつね」の文章に問題があるから。
そこで、ごんぎつねの物語世界を考察してみたい。
「ごん」という悪戯好きの狐がいた。
秋のある日、兵十という男が川で漁をしていた。
それを見かけたごんは、兵十が席を外した隙に忍び込み、彼がせっかく捕らえた魚を台無しにしてしまった。
以下、物語本文に交えて状況の解説。
十日ほどたって、ごんが、弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの、いちじくの木のかげで、弥助の家内が、おはぐろをつけていました。
明治以前の既婚女性は、植物の渋や鉄さびを混合した染料で歯を黒く染めていた。それが「お歯黒」。だが現代的な美意識にはそぐわないため、時代劇でも意図的に無視されている風習。
もっとも毎日歯を染めるのは手間ゆえ、庶民の間では「特別な日」のみ歯を染めるものだった。
鍛冶屋の新兵衛の家のうらを通ると、新兵衛の家内が髪をすいていました。
髪はとかすもの、あるいはブラッシングするもの。「梳く」という表現はもはや死語である。
ごんは、「ふふん、村に何かあるんだな」と、思いました。
今はすたれた風習に言葉。それでも女性が装っていることが読み取れる。村が「非日常」にあることが予感される。
「何だろう、秋祭かな。祭なら、太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮にのぼりが立つはずだが」
その非日常は村祭りではない。笛や太鼓の音は聞こえない。
こんなことを考えながらやって来ますと、いつの間にか、表に赤い井戸のある、兵十の家の前へ来ました。その小さな、こわれかけた家の中には、大勢の人があつまっていました。
村人は兵十の家に集まっている。イベントの舞台は兵十の家である。
ここまで、兵十という人物についての情報はほとんど明かされていない。
男性であること。
経済的には恵まれていないこと。
その程度しか推察できない。
家族構成はどうなのか。
青年なのか、中年なのか、老人なのか。
それすらも分からない。
よそいきの着物を着て、腰に手拭をさげたりした女たちが、表のかまどで火をたいています。
その兵十の家に「よそ行きの着物」を着た村の衆が集い、忙しく立ち働く。
兵十が独身の若者ならば(実際そうなのだろうが)、「嫁取り」という展開も予感できよう。
「オラのかわいい嫁っ子にご馳走しようとした鰻を台無しにしやがった!このクソ狐が!」などというストーリーもありえよう。それならばごんは微塵も反省することなく、「トムとジェリー」のようなドタバタが延々と演じられるのだろうか。
大きな鍋の中では、何かぐずぐず煮えていました。
「ああ、葬式だ」と、ごんは思いました。
「兵十の家のだれが死んだんだろう」
外のかまどでは「何か」が煮えている。
その「何か」を見て、ごんは「葬式だ」と悟る。
「よそ行きの着物」は「喪服」とは明記されていない。
素木の棺桶もない。
僧侶の姿もない。
念仏の唱和も聞こえない。
だが「煮える何か」で「葬式」だと悟る。
鍋の中の「何か」が死を濃厚に漂わせていたのだ。
「ぐずぐず」などという、およそ食欲をそそらないオノマトペを添えられて。
お午がすぎると、ごんは、村の墓地へ行って、六地蔵さんのかげにかくれていました。いいお天気で、遠く向うには、お城の屋根瓦が光っています。墓地には、ひがん花が、赤い布きれのようにさきつづいていました。と、村の方から、カーン、カーン、と、鐘が鳴って来ました。葬式の出る合図です。
やがて、白い着物を着た葬列のものたちがやって来るのがちらちら見えはじめました。話声も近くなりました。葬列は墓地へはいって来ました。人々が通ったあとには、ひがん花が、ふみおられていました。
ごんはのびあがって見ました。兵十が、白いかみしもをつけて、位牌をささげています。いつもは、赤いさつま芋みたいな元気のいい顔が、きょうは何だかしおれていました。
「ははん、死んだのは兵十のおっ母だ」
ごんはそう思いながら、頭をひっこめました。
昼下がり
鐘の音を合図に、野送りの行列が出発する。
秋空に光る城の瓦屋根
白装束の村の衆
踏みしだかれる彼岸花
白裃の兵十は、素木の位牌を捧げ持つ。
青空
光る瓦屋根
彼岸花の赤
そして白装束
行列が通れば彼岸花の赤は泥にまみれる
「色彩で統一された様式美」
文学的にはそのように解釈できよう。
「喪服は、江戸期までは白装束だった。だが明治以降、欧米の影響で黒服に様変わりした」そんな「葬送習俗の変遷」の一例にもなりえよう。
だが肝心の「遺体」「棺桶」の存在が伺えない。
ここで
「おっかあの体を納めた素木の棺桶は、太い棒を通されて、二人がかりでかついで運ばれていきました。担ぎ手が足を進めるたびに、ぶらりぶらりと揺れていました」
「地面を六尺も掘り上げた深い穴の中に、棺桶が納められていきました。村の衆が埋めにかかります。棺桶の蓋は落ちる土を受け止めてごとりごとりと鳴るうちに、すっかり見えなくなりました。兵十はうっうっと声を殺して泣いています」
あるいは
「焼き場の石組みの中に積み上げた薪の上に、棺桶がのせられます。続いて山のような藁で覆われていきました。水に漬けたむしろを最後に乗せ、西の方角から松明で火を入れます…勢いを増す炎を浴びて、兵十の涙が黄金色に輝いて落ちました。夜通し燃え上がる火は、ごんの巣穴からもよく見えました」
などという描写でもあれば、「おっかあの死体を煮ていた」と誤解しかけた子どもでも「軌道修正」できよう。何を煮ていたのかはさておいて。
だが本文の野送り行列を読む限りでは土葬かも火葬かも、棺桶の存在もうかがえない。
おっかあの死は「白木の位牌」にのみ集約されている。
日本の伝統的な葬送儀礼を知りえない年代であれば
「おっかあの遺体を煮込んで、村の衆みんなでおいしくいただいちゃいました。兵十のおっかあの遺徳は、わたしたちの心に宿りました。おっかあは死んでも、私たちの心の中で生き続けます。
…だから、葬式行列に棺桶はありません」
などという解釈も成り立つわけである。
「食べて弔う」
そんな風習も世界にはある
昭和50年から見て近未来。
戦前生まれの最後の年代が、ちょうど定年の55歳を迎えるその時代。日本は食糧難にあえいでいた。その解決策として、画期的?な法案が施行された。
その日、55歳の定年を迎えた主人公は一族郎党に心を込めた「お・も・て・な・し」された後に…
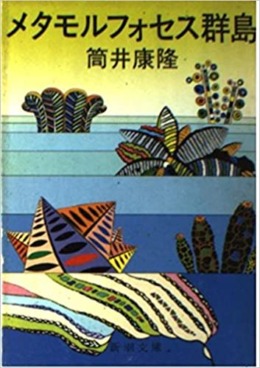
筒井康隆の問題小説「定年食」
(新潮社文庫『メタモルフォセス群島』に収録)
さすがにお子様には刺激が強すぎる小説だが、このような考えもたしかに存在するのである。
ごんぎつねの舞台は、尾州知多郡の岩滑(やなべ)。
現在の愛知県半田市郊外。
上記のような「食べて弔う」葬送儀礼が過去にあった試しがない。
現代的な葬送儀礼として生まれるはずもない。
だが文化人類的に世界を俯瞰すれば、「食べて弔う」儀式は確実に存在していたからして難しい。(詳しくはネット検索してください)
「食べて弔う」
日本において実例がなくとも説話の中では、例外ではない。
柳田国男の『遠野物語拾遺』より

五月五日は薄餅を造る。
薄餅というのは、薄の新しい葉を刈って来て、それに搗き立ての水切り餅を包んだもので、餅が乾かぬうちに食べると、草の移り香がして、なんとも言えぬ風味がある。
薄餅の由来として語り伝えられている話に、昔或所に大そう仲のよい夫婦の者が居た。夫は妻が織った機を売りに遠い国に行って幾日も幾日も帰って来なかった。其留守に近所の若者共が、此女房の機を織って居る側へ来て覗き見をしては、うるさいことを色々したので、女房は堪りかねて前の川に身を投げて死んでしまった。
恰度旅から夫が帰って来て此有様を見ると、女房の屍に取りすがって夜昼泣き悲しんでいたが、後に其肉を薄の葉に包んで持ち帰って餅にして食べた。是が五月節句に薄餅を作って食べるようになった始めである。
七月七日には是非とも筋太の素麵を食べるものとされて居る。其由来として語られている譚は、五月の薄餅の後日譚のようになって居る。夫は死んだ妻の肉を餅にして食べたが、其うちから特別にスヂハナギ(筋肉)だけを取って置いて、七月の七日に今の素麺のようにして食べた。是が起こりとなって、此の日には今でも筋太の素麺を食べるのだと謂う話である。
人体は巨大なタンパク質の塊である。農業や牧畜技術が未発達だった時代。民衆の大半が栄養不良に甘んじていた時代。肉親の死という形でタンパク質が提供されたならば…
そのような展開も充分に予感される、ともいえよう。
鍋の中で「ぐずぐず」煮えていたものは?
愛知県の食文化から真面目に考察
だが上記の逸話は「カチカチ山の○○汁」同様、あくまでも「昔話」というフィクション。重ねて言うが、本邦に「食べて弔う」葬式は存在しない。ごんぎつねの作者、新美南吉の出身地である愛知県知多郡岩滑の村でもそれは同様である。
しかし、ごんは鍋の中身で「不祝儀」を悟った。
死を濃厚に漂わせるものが、やはり大鍋の中にあったのだ。
一部ネットでは、鍋の中身は「涙汁」ではないか、との意見がささやかれている。唐辛子粉をたっぷり振りかけた薄い味噌汁。葬儀の際はこの辛い汁を振舞い、皆で思いっきり涙を流す。だが葬儀に涙汁を仕立てるのは、愛知県でも西部側、三重県や岐阜県との県境に近い地域、ちょうど木曽三川の水郷地帯に当たる一帯である。半田市が位置する知多半島東岸とはかなり距離がある。
そもそも煮えるオノマトペが「ぐずぐず」
汁物が沸騰する音感には似つかわしくない。
ここで、愛知県の食文化を詳細に改めてみよう。
すると「こも豆腐」という食品が浮上する。
豆腐を藁苞か巻き簾に包んで茹でたもの。豆腐は茹でることで余分な水分が排出されて身が締まり、全体的にス(すき間、気泡)が入る。スの入った豆腐を改めて出汁で煮含め、口中に投じて舌を押し付ければ、お出汁がじゅわっと溢れる。

「こも豆腐」でネット検索すれば、まずは岐阜県飛騨地方の食文化がヒット。当地の名物料理としてネットでも購入できるが、こも豆腐は飛騨地方のみの食文化ではない、東は茨城県に、もちろん岐阜の隣県である愛知にも伝承されている。
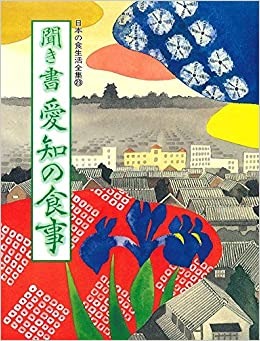
農文協『日本の食文化全集 愛知の食事』
半田の街のある愛知県知多半島を南に向かえば、先端は南知多町。当書籍では、南知多町の食文化が章をもうけて解説されているが、当地において「こも豆腐」は葬儀の定番料理だった。「あの人も豆腐にならした(なられた)」と言えば、「他界」の婉曲表現となる。

こも豆腐を作る。豆腐を藁苞で包んで煮る…
ハタ目には、巨大なミノ虫が鍋で煮えているようにしか見えない。パッと見には「何か」としか言いようがない
鍋の中では何かがぐずぐずと煮えていました。(ここは、「ぐずぐず」でも構わない)。ごんが目を凝らしてよく見てみますと、鍋の中では藁つつみがいくつも湯だっていました。
「ああ、葬式だ」と、ごんは思いました。
あるいは全国的に冠婚葬祭や正月のごちそうとして定番だった「煮〆」かもしれない。

写真はウィキペディア、©Ocdp
ダイコンに人参、里芋、牛蒡、シイタケ、コンニャクに練り物、焼き豆腐を醤油味でじっくり煮含めた「おふくろの味」の定番。正月や結婚式など慶事の煮〆は、「末永く」の縁起をかついてコンニャクは「手綱こんにゃく」に加工する。ニンジンは梅や桜、あるいは亀甲を模した飾り切りにする。
一方で不祝儀の折は、飾り切りなど持ってのほか。素材も肉や練り製品など動物性タンパク質の「なまぐさ物」は論外。出汁も鰹節や煮干しは使わず昆布かシイタケで引くなど「精進」を徹底させる。そして葬儀の「白装束」にちなみ、色濃い味付けは忌まれる。
この項を書くにあたり『半田市誌』はじめ、阿久比町、常滑市、さらに知多半島南端、南知多の市史や町史の民俗誌は改めた。
あいにく「半田」では詳しい葬式料理の記述はない。南知多では「名物のこも豆腐」、常滑では「ひりょうず(がんもどき)や野菜の煮物」、そして阿久比では「野菜の煮物」とある。阿久比の表記は詳しく、「戦後では精進料理にこだわらず、『トンカツ』『刺身』も膳に上る」「仕出し料理店で三千円程度のメニューを注文し…」あくまで戦後の話。
火縄銃があり南米原産の甘藷が普及している江戸時代なら、「野菜の煮しめ」で間違いはないだろう。
鍋の中では何かがふつふつ(さすがに『ぐずぐず』では食欲をそそらないので)と煮えていました。お煮しめだ、とごんは胸いっぱいに甘い出し汁の香りを吸い込みました。ふと、不思議なことに気が付きました。
年越し祝いや嫁入りのお振舞いなら、煮干しで取る煮しめのお出汁。でも、鍋の中から、ごんの大好きな魚の香りがしません。大鍋で煮えている煮〆のおつゆは、昆布とシイタケを煮出したもののようでした。よく目をこらして鍋の中をのぞいてみますと、お祝いの時は梅や桜の花びらの形に切る人参も、亀の甲らの六角形にととのえる芋もしいたけも、ぶあいそうに輪切りにされているだけでした。
「ああ、葬式だ」と、ごんは思いました。
日本の民間信仰における「神獣」である狐。ごんは人間と同等、あるいはそれ以上の知能を有している。
当然、居住地域であるところの尾張国知多郡岩滑における、人間世界の葬送儀礼も熟知していたことだろう。
生物学的に言うところのホンドキツネの嗅覚は、人間の1万倍にも及ぶという。出汁を嗅げば、その素材を嗅ぎ分けただろう。煮干しか、鰹節か、昆布の精進出汁か。そして人間世界の習俗とつなぎ合わせて、料理から「冠婚葬祭」を推察することができる。
嗅覚と知識で、冠婚葬祭を瞬時に判断できる
ごんぎつねは「海原雄山の前世」であろうか。
でも読者の大半には鋭敏な嗅覚味覚も、当地の葬送儀礼の知識もない。
作者・新美南吉には、ぜひとも「ぐずぐず煮える葬式料理」の詳細を書いていただきたかった。未来の読者が妙な誤解をしないためにも。
※本文中の斜体は、筆者の咄嗟の創作です
※本文中の太字は、
「『ごんぎつね』の読めない小学生たち」(文春オンライン)
「ごんぎつね」(偕成社)
「遠野物語 ―付・遠野物語拾遺」(角川ソフィア文庫)
からの一部引用文となっています








