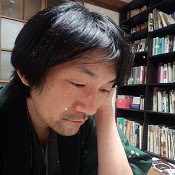サザエさんちのお雑煮は関東風?九州博多風?
日本の「理想的な一家」とされているサザエさん。
日本的な家庭だからこそ、正月前には一家の大掃除、
羽子板出して、暮れには一家総出で障子貼りに餅つき、門松かざり
そして年が明ければ羽根つきにかるた取り。
まったくもって日本的なお正月。
さてお正月と言えば外せないのが「お雑煮」。磯野家も当然、元日は一家総出でお雑煮を祝うのであろう。問題は「磯野家のお雑煮は?」ということなのである。
お雑煮
餅を入れた汁物
日本全国的、厳密に言えば大和民族に等しく伝わる正月料理である。
だが「等しく伝わる」とはいえ、地方ごとに千差万別。
「出汁は何で取るか」
「汁の味付けは、味噌か、それとも醤油か」
「餅は切り餅か、丸餅か」
「餅は茹でるのか、焼くのか」
「具に何を入れるのか」
「中心となる具は何か」
これだけで地方ごと、さらには家庭ごとで千差万別。
だから大手食品メーカーがいくら「おでんセット」「寄せ鍋の出汁」を商品として提供したとて、「お雑煮セット」「お雑煮の出汁」だけは商品化できない。地域限定の中小メーカーならともかく、全国をカバーできる味を、具を提供できないからだ。
でも地方ごとにパターンはある
北日本から東日本は具だくさんの澄まし汁に、焼いた切り餅
北陸から中部地方は澄まし出汁。餅を焼くか、煮るか。切り餅か丸餅かは混在
近畿地方は味噌仕立ての汁に茹でた丸餅
中国地方では澄まし汁に茹でた丸餅。一部では雑煮ではなく「小豆ぜんざい」
四国は瀬戸内地方は味噌仕立ての汁に茹でた丸餅、あるいは餡餅。太平洋側ではすまし仕立ての具だくさんに茹でた切り餅
九州は北部で茹でた丸餅、南部は焼いた切り餅。汁はおしなべて澄まし仕立て
日本本土と文化が異なる沖縄では、正月に「餅を入れた汁物」を味わう習慣が無い。
北海道では先住民のアイヌ民族には「正月」を祝う習慣がもともと無く、シト(餅、団子)を入れた汁物、という料理もない。そして明治以降に入植した開拓民の家系では「内地の出身地ごと」の雑煮を作る。同じ村でもあの家は越中衆だから澄まし仕立てに茹でた切り餅、焼き魚をほぐして入れる。隣は阿波衆だから味噌仕立て、まさに家ごとに千差万別…
さて、磯野家のお雑煮
サザエさんちは一応、世田谷の桜新町にあるとされている。
だから関東、東京風の正月を迎える、と思われるかもしれない。
実際に正月を迎える場面でもマスオが餅を搗けば、搗きあがった餅を延し板に延ばして多少乾燥させる。これを規格ごとに裁断すれば「切り餅」の完成。
伸ばした餅に猫やワカメが足跡をつけてしまったり、乾燥させ過ぎでガチガチになった延し餅を切りわけるピンチヒッターとしてノリスケが呼ばれたりとひと騒動だが、大量に搗かれた餅は正月を越しても食膳に並び、ウンザリしたカツオがヒキツケを起こすありさまともあれ磯野家の餅は関東風の切り餅である。
ならばやはり磯野家のお雑煮は関東風、東京風だろうか。
カツオか昆布の出汁の澄まし汁、具は鶏肉に青菜に椎茸にカマボコ、そしてカリッと焼いた切り餅入りだろうか。
だがそうとも言い切れないもどかしさ。おそらく昭和30年代の作品だろうか、正月気分が抜けきらず炬燵でゴロゴロ、紙風船で遊ぶサザエを波平が?りつける。
「おまえ、とかけて、煮すぎた雑煮のモチと解く」
「そのこころは?」
「すくいがたい」
台所で顛末を聴いていたフネが
「あんなしかり方して、お父さんも正月気分が抜けてないのね」とあきれてオチ
雑煮餅は煮るもの。煮すぎた餅はベタベタに溶けて掬えない。
磯野家の雑煮餅は「煮る」ものなのである。
ここで一旦、「サザエさん」の作者であるところの長谷川町子の人生を探ってみたい。
大正9年、九州は福岡市に三人姉妹の次女として生まれた町子。14歳の折、父の死去に伴い母や姉妹と共に上京し、「のらくろ」の作者である田川水泡に弟子入り、昭和10年「少女倶楽部」誌上で「狸の面」なる見開き漫画でデビューする。太平洋戦争中は故郷・九州福岡に疎開。終戦後も福岡で引き続き暮らし翌昭和21年、当時福岡県に存在した地方紙・フクニチ新聞における「夕刊紙の新聞漫画」の仕事を受け、ここに「サザエさん」誕生。登場人物の名前がみな海由来なのは、海岸を散歩して構想を練ったが故と言う。だがほどなく町子と姉の毬子はそろって首都圏の有名出版社から依頼を受け、九州の地方紙での掲載は「サザエの結婚」をもっていったん打ち切りとなった。
そして紆余曲折を経つつも昭和24年より「サザエさん」は朝日新聞夕刊において連載再開。舞台を東京に移して家族のユーモア、後には時事問題やブラックネタもからめつつ25年間、昭和49年に至るまで続いていく。
長谷川町子は九州福岡生まれ
サザエさんは九州福岡生まれ
ここで九州北部・福岡市の雑煮を探ってみたい。
福岡の雑煮は「博多雑煮」と称され、京都の白味噌雑煮や讃岐の餡餅雑煮と並んで有名である。
アゴ(トビウオ)の煮干しで引いた出汁に醤油味の澄まし汁。
具のメインは塩ブリ。戻し椎茸にカマボコ、豆腐。そして九州北部限定の野菜・カツオ菜。
肝心の餅は、茹でた丸餅だ。
https://www.youtube.com/watch?v=Xxb_nWE9y5o
磯野家の雑煮餅は、煮る物なのだ。
長い関東暮らしで、磯野家は故郷の習慣を忘れてしまった。
丸餅文化圏の九州北部ながら、磯野家の正月準備は「切り餅」作り
ご先祖の墓参りに九州に帰省する描写はなく、近場の墓で済ます。
挙句は夢に現れたご先祖の「庭の隅に小判が詰まった壺を埋けておいた」の言葉を信じ込んで「東京の家」の庭先を掘り返す波平。故郷の福岡を忘れて…
それでも雑煮餅は「煮る」。
磯野家の雑煮は博多式なのだろうか。
アゴ出汁に塩ブリ、カマボコにカツオ菜。
茹でた丸餅。
令和より格段に流通が乏しかった昭和中期の東京
でもトビウオの煮干しは乾物屋に都合すれば用意できるだろう。
現在では関東圏のスーパーでも新鮮な状態で売られるカツオ菜だが、さすがに昭和期では心もとない。これは小松菜かホウレンソウで代用か。
問題は餅…
マンガでは、磯野家の餅はみな切り餅だ。
お雑煮用に、特別に丸餅を誂える描写は筆者が知る限りはない。
切り餅を煮すぎないように温めた上で乗せた「博多風雑煮」だろうか
謎が深まる、磯野家のお雑煮。
※メイン画像は農林水産省ホームページ
「うちの郷土料理~次世代に伝えたい大切な味~ 福岡県「博多雑煮」レシピムービー」よりスクリーンショット